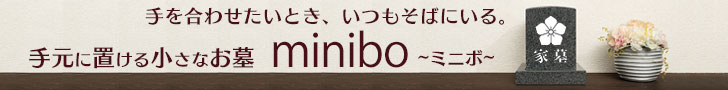墓は故人を供養するとともに、先祖と自分を繋ぐ心の拠り所として大切な場所でもあります。
しかし、親が亡くなった時安置する墓が無いと困りますよね。
代々の墓があれば別ですが、そういった墓が無い場合墓を準備しなければなりません。
親が事前に準備していれば良いですが、多額の費用もかかるのでなかなかできるものではありません。
そうすると亡くなってから遺骨をどうするかという問題が出てきます。
この記事では、こういった墓を持たないという選択をした場合にどういった供養方法があるかを解説していきます。
墓を持たない(作らない)場合に故人を供養する方法
墓を作らずに故人を供養しうる方法は次の6つです。
- 自宅で保管
- 納骨堂
- 共同墓地
- 樹木葬
- 海洋散骨
自宅で保管

遺骨を自宅で保管する、手元供養と呼ばれる方法です。
遺骨は骨壷に入れて保管する方法のほか、花器などのインテリア用品に遺骨を入れて供養する。またはペンダントやブレスレットなどのアクセサリーに入れて身につけるという方法もあります。
故人を身近に感じたいと思われる方には良い方法です。
ただ、親族などから反対される場合もあるので、事前によく話し合っておくことが必要です。
納骨堂

納骨堂とは、屋内施設で決められたスペースに遺骨を安置する供養方法です。
子供や孫に負担をかけたくない、墓所の確保が難しいなどの理由で近年増加傾向にあります。
コインロッカーのように扉付きで同じ大きさのスペースが並んでいるタイプや、参拝ブースでICカードをかざせばバックヤードから遺骨が自動搬送されてくるようなハイテクな納骨堂まで様々なタイプがあります。
運営も、寺院、自治体、宗教法人の3種類あります。
納骨堂は比較的アクセスがしやすい立地が多く、天候を気にせずお参りできるのが魅力です。
共同墓地

共同墓地とは、寺院や霊園といった管理者が一括して管理するお墓です。
供養塔などがあり、そこに家族以外の方達と一緒に入ることになります。
お盆やお彼岸に合同で供養していただけますが、個別に年忌法要などを行なってほしい場合は別途依頼しないといけないケースが大半です。
縁のない方と一緒にお墓に入ることになるため、家族や親族から反対されるケースあるようなので、事前によく話し合っておくことが必要です。
樹木葬

樹木葬は、1999年に岩手県の寺院 大慈山祥雲寺(現:長倉山 知勝院)によって栗駒山山麓につくられたのが始まりです。
その後、各地で広がりを見せている新しい供養スタイルで人気も高まってきています。
樹木葬は、自然の中で穏やかに眠り自然に還ることをコンセプトとしている霊園が多いため、骨壷から遺骨を取り出し埋葬するのが一般的です。
ただ、樹木葬と言っても種類があり、埋葬方法やシンボルとする植物の種類など、それぞれ違いがあるので、希望する場合は運営する霊園等に詳細を聞いた方が良いでしょう。
海洋散骨

海洋散骨も1990年代から実施されている比較的新しい方法です。
海洋散骨は故人の希望によるところが多いようですが、実施するには色々な手配等が必要なため専門の業者に依頼した方が良いです。
ただ、全部海に撒いてしまうと取り戻すことが不可能なため、一部をインテリアやアクセサリーに収容する方法も検討の余地がるでしょう。
まとめ
遺骨を埋葬する方法は、以前は墓に安置する方法が一般的でしたが、最近では上述のように色々な方法があります。
逝く側、送る側の両方が納得できるような方法で供養することができれば幸せですね。
この記事が参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。